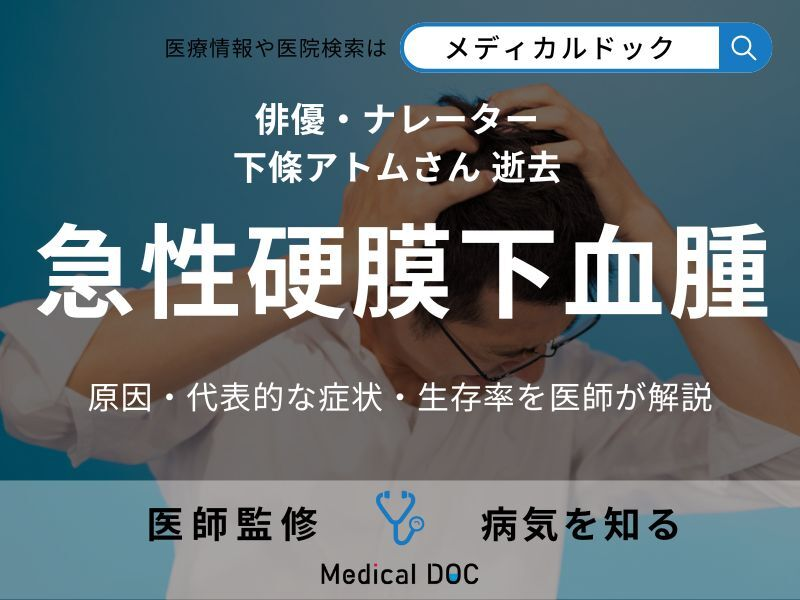急性硬膜下血腫とは、転落や転倒、時に交通事故などの外的な影響によって頭部へ強い衝撃が加わったために、脳を守る一番外側の膜である「硬膜」の下に出血が生じておきる病気です。ここでは急性硬膜下血腫の症状や原因、治療などについて解説していきます。
急性硬膜下血腫は、硬膜と呼ばれる膜の下と脳の表面との間にある血管が切れて出血することで生じます。主な症状は、出血による脳や硬膜への圧迫や圧力の高まりによって生じる「頭痛」や「嘔吐・吐き気」、「運動麻痺」などが挙げられます。さらに出血量がとても多い場合は、脳に急激かつ強い圧迫が加わり、「脳ヘルニア」と呼ばれる脳の変形を生じてしまいます。この「脳ヘルニア」になると、重篤な意識障害をきたし、命に関わるような非常に危険な状態に陥ります。 主な原因は頭部への打撃によるもので、その場合は急性硬膜下血腫のみでなく、頭蓋骨の「骨折」を合併していたり、脳自体が直接損傷して出血する「脳挫傷」やくも膜と呼ばれる膜に存在する血管が切れて出血する「外傷性くも膜下出血」といった脳への損傷を合併していたりする場合もあります。そういった合併症がある場合には症状がより複雑化し、重篤な状態に陥る危険性も高まります。とにかく頭に外傷を受けた後に普段と様子がおかしい、ボーっとして朦朧状態である、といったことが見られる場合はより危険なサインです。直ちに脳神経外科や救急科への救急搬送が必要となります。また脳への打撃が高度であった場合は痙攣発作を生じる場合もあり、痙攣によって呼吸停止に陥る危険性もあります。従って重度の昏睡状態や痙攣などを起こしている場合は、急変して死亡する危険性が高いため、緊急の気道確保を行い人工呼吸器による呼吸の補助や痙攣を抑える薬剤の投与を行う場合もあります。
Page 2
[軽度の場合] 軽度の急性硬膜下血腫とは、もともとの出血量が少なく、入院後の繰り返しのCTでも出血の量が増えてこなかった場合です。安静にし、出血を抑えるような点滴などをして、1週間程度の入院で退院することが可能です。もちろん脳挫傷などが併発していたり、少しでも後遺症が残ったりしそうな場合は入院期間とリハビリを長めにとることもあります。また若年者でスポーツに関連して急性硬膜下血腫を発症した場合、例え軽症であっても、もう一度頭部への打撃が生じてしまうと急激に状態が悪化する危険性があるため、競技への復帰が困難になる可能性があります。 [重症の場合] 重症の急性硬膜下血腫は、痙攣や重度の昏睡状態に陥っている場合、経時的に出血が拡大し、脳への圧迫が高度となり脳ヘルニアに至る危険性がある場合、重度の脳挫傷や外傷性くも膜下出血の合併がある場合などです。これらの場合は緊急手術を行う可能性が高いです。具体的には開頭血腫除去術といって、出血がたまっている側の頭蓋骨を医療用のドリルを用いて外し、硬膜の下の出血や合併している脳挫傷による脳の中の出血を除去し、止血を行います。さらに出血によって圧迫された脳が腫れてくる場合もあります。この場合は腫れてきた脳が正常な部分の脳を圧迫して脳ヘルニアになる危険性があるため、外減圧術という脳が腫れている側の骨を大きく外して、脳が腫れている圧力を外側に逃がす手術を行う場合もあります。また集中治療室に入院し、全身麻酔をかけて人工呼吸器による呼吸補助をはじめとした全身管理を行い、脳の圧力を監視してコントロールするような集中的な治療を行う場合もあります。 [リハビリによる治療] リハビリは「リハビリテーション科」という診療科が主に担当し、医師や看護師のほかに理学療法士、作業療法士、言語療法士と呼ばれるリハビリに特化した役職の人も所属しています。そして救急科や脳神経外科と協力して入院治療を進めます。患者さんの状態が落ち着けば、本格的なリハビリが始まります。またリハビリ治療に特化した「回復期リハビリ病院(病棟)」というものがあり、後遺症が中等度から重度の場合はそのような機能のある病院(病棟)に移動(転院・転棟)して、さらに集中的なリハビリを行います。後遺症の程度によりますが、リハビリ期間については数か月から半年程度までおよぶ可能性もあり、その後も長期の福祉・介護施設やサービスの利用が必要となる場合もあります。 例えば運動麻痺を残した場合、歩行訓練や手先を使った作業訓練を行ったり、歩行を補助する装具や杖などを使用したりすることもあります。嚥下障害がある場合は、食べ物が肺や気管に入って窒息や誤嚥性肺炎と呼ばれる肺炎を引き起こす恐れがあるので、食事を柔らかくするなど、飲み込みの訓練を行います。家族は自宅や職場の階段や段差など歩行に障害となる環境がないか、またトイレやお風呂の環境なども確認しておきましょう。また後遺症の程度によっては障害者認定や介護認定の申請も重要です。認定が下りれば、利用できるサービスが広がります。 また記憶障害や空間認識力、認知機能、言語能力など、高次脳機能障害と呼ばれる機能に関連する後遺症が残った場合は、見た目ではわかりづらく、またそれぞれの症状にあったリハビリが必要となります。例えば記憶障害がある場合、メモや手帳などを利用したり、家族や職場の人が繰り返し教えてあげたり、といったことです。また空間認識や注意力が低下している場合は、認識しやすい位置に物を置いたり、作業を1つにして簡略化したり、といったことも大切です。いずれにせよ作業療法や言語療法というリハビリを通じて、自宅や施設でより良く生活するための手段を考える必要があります。
*******
****************************************************************************
*******
****************************************************************************